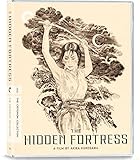黒澤明「隠し砦の三悪人」(1958)美しい姫とお家再興の為の「正義」と「悪」、弱い故に貪欲な者への優しい視線。
2024/08/13
黒澤明「隠し砦の三悪人」を観た。とにかく面白くて、魅力に溢れている。これを超えるような深みのある作品を、黒澤明はたくさん撮っているけれども、この映画をして、黒澤明の最高傑作なる視点があっても驚かない。それくらい、ある種の完成形を見せられる思いがした。「蜘蛛巣城」(1957)と「隠し砦の三悪人」(1958)と連続で観ると、映画の喜びがすごくて、いい夢を見て目覚めたときの感じに似ている。
お話は、お家を再興しようとしているお姫様とその家来たちが隠し砦にいて、軍資金を金にして小枝に隠してある。そこに農民二人が偶然辿りついて、家来の筆頭格であり、姫のボディーガードでもある三船敏郎演じる剛の者と合わせて、三悪人となる。追手を逃れて、三悪人と姫が、関所を突破し、様々な難関をくぐり抜けていくというものなのだが、一対一の戦いあり、馬上の戦いあり、人間心理あり、お祭りがあり、歌があり、これまで同様の黒澤明映画でありながら、熟練によって凝縮されたエッセンスと移動が、軽快であり、美しい。黒澤明映画をこうして連続で観ていると、移動や旅を描くような作品は少ないような気がする。「羅生門」は門と登場人物の回想であるし、「七人の侍」は村にずっといる感じであるし、「蜘蛛巣城」は城と森である。「赤ひげ」は療養所がほとんど全てであるし、大体、ひとつの場所を中心として、そこに深くのめり込ませる。まるで実在する舞台のように、観客をそこに入れこむ、というのが黒澤明の十八番だと思う。それに対して、「隠し砦の三悪人」は、砦を出てしまう。あろうことか、砦は炎上さえする。そして、旅の一行となるのだ。黒澤明映画としては、めずらしいように感じる。旅をしている感じがして、舞台が広く感じられるのである。いつもの黒澤明なら、隠し砦で最初から最後までいきそうな感じがするのだが、あれ、という驚きがあった。

黒澤明の晩年の作品は、圧倒的な美しさを持っており、芸術作品として高く、魅力的であり、生きる指針になりえるような宝物なのだが、時々、晩年の黒澤明は、全くだめだ、というようなことを言っている方がいて、わたしとしては、はてな?どうしたらそういう見解になるのか不可思議であったのだが、少しずつわかってきた。「蜘蛛巣城」「隠し砦の三悪人」「用心棒」「椿三十郎」というようなラインナップは、素晴らしい作品であると共に、わかりやすい。このような作品を良い映画として、黒澤明に期待する者にとっては、晩年の芸術的な作品は、むしろ不可解との印象だったのだろう。わたしは、「まあだだよ」に感服して、既に五回以上見ているが、やっぱり「まあだだよ」のラストが最高峰である。この上なく美しく、面白く、深みがある。「まあだだよ」を超える作品というのは、今のところ、わたしの中では皆無である。しかしながら、この「隠し砦の三悪人」は、映画文法に習熟してきた黒澤明が、娯楽作品を撮ったものとしては、最上のものと言えると思う。農民二人の貪欲も、コミカルに描かれて、黒澤は、そこに距離を置いて描いている。愚かで貪欲で、しかしながら、それも弱い人間の真実であれば、優しい目線がそこに注がれ、芸術をよく理解出来ない人たちに対しても、同様の優しさが、この映画の軽さに現れているのだと思われる。
弱さゆえに貪欲な農民二人と対照的に、強さと信念を持った三船敏郎演じる真壁と姫、この対照が、作品を広くしていることも見逃せない。姫の発声や態度は、素晴らしい。決然とした人物像が立ち上がっている。女性がこのように存在感を示す作品も、黒澤映画の中では稀ではないかと思う。三悪人は、この農民二人と三船敏郎をして、三人なのだと思うが、ひとつ面白いのは、お家再興への道筋が成り、姫と三船敏郎ともう一人途中で仲間になった男が、三人で、屋敷に並び立っているラストの場面である。まるで、この三人こそが、三悪人なのかな、という印象さえ持たせる。何が悪人なのか。三船敏郎演じる真壁は、多くのトリックを使って難局を切り抜ける、あるいは敵を倒す。途中で仲間になった男は、敵方から見れば裏切者である。姫は耳が聞こえないふりをして農民をだましていた。言おうと思えば、彼ら三人もまた悪人なのである。農民の二人はまた、お互いに欲張って喧嘩するし、姫や真壁を何度も裏切ろうとした悪人である。一年前には、「蜘蛛巣城」で、権力争いが描かれた。城主は、以前の城主を暗殺していた。そして、三船敏郎もまた、城主を殺害して、自らが大殿になる。お家を再興するということは、姫や真壁にとって正しいことで善であり、良いことであろう。そのためには、敵を滅ぼすこともあるだろう。実際に血が流れている。つまり、善なることを為すために、多くの悪が為される。アメリカは、広島と長崎に原爆を落とした。これは非人道的な行為であり、悪であろう。しかし、戦争に勝った以上、彼らが正義であり、日本の軍人たちは、裁かれ、戦犯として処された。蘇我馬子が天皇を暗殺することによって、聖徳太子の摂政の道が開けた。蘇我入鹿が中大兄皇子らに暗殺されて大化の改新が成った。お家を再興するために、その善のために、当然悪も為さねばならない。「蜘蛛巣城」では、そうした権力争いをする人間心理に焦点が当たっていた。「隠し砦の三悪人」では、その点は、微かな片鱗に留められている。そうでなければ、痛快な娯楽にはならないからであろう。しかし、わたしたちは、黒澤明映画の真髄を既に観ている者であるから、このまま黒澤明が、一方のみを格好良く正しいように描くようなことをするのだろうか、とも思う。清濁併せ呑むような東洋の国を描いてきて、トルストイやドストエフスキーやゴーリキやシェイクスピアを原作として映画を撮ってきた男が、追う者と追われる者、殺す者と殺される者の秘かな同一性を理解していないはずがないのである。タイトルに、わざわざ「悪人」とつけるのは、平板に勝った者が偉いような映画を撮ったことへの、一種の羞恥心、バランス感覚がせしめたこととわたしは思う。「三悪人」という映画へのオマージュという話だが、それだけでもあるまい。夏目漱石が、善と悪が入り混じった人間と書いたように、善と悪は、きっぱり分けることは出来ない。それを分けようとするのが、合理思考のメガネである。それは乗り越えられなければならない人類の課題であり、はやくから黒澤明は、直観的にそこに着目している。あるいは文学的素養に拠るかもしれない。「用心棒」「椿三十郎」では、三船敏郎は、同じように強い英雄像を演じる。しかし、争う敵と味方の両方に接触することのできる境界人として描かれている。娯楽作品を描いていても、微かな水が流れ、それは、やがて「赤ひげ」の救世主像にまで発展していく。
火の祭りのシーンは、映画的な見どころを創ると共に、深遠な人間の姿を映し出してもいる。この列島には、一万年以上縄文人が暮らしていた。彼らの文化は、今でも日本人に決定的な影響を与えているが、このような太古由来の祭りも実際にあっただろうと思わせる。その歌の内容がまた、黒澤明の祭り理解の高さを示していて興味深い。
人の命は 火と燃やせ
蟲の命は 火に捨てよ
思い思えば闇の夜や
浮世は夢よ ただ狂え
これぞ、祭りという感じである。そして、姫は、死が近づいたとき、祭りが楽しかったとして、これを歌う。なんと深みがあり、心染みる場面であろうか。ただの娯楽作品には終わらないものが、随所にちりばめられて、この映画は、娯楽と作家性が見事な融合を果たした傑作と言うべきなのかもしれない。軽さだけを観たい者には、軽さを。深みが欲しい者には深みを。両方兼ね備えていると言うことなのかもしれない。